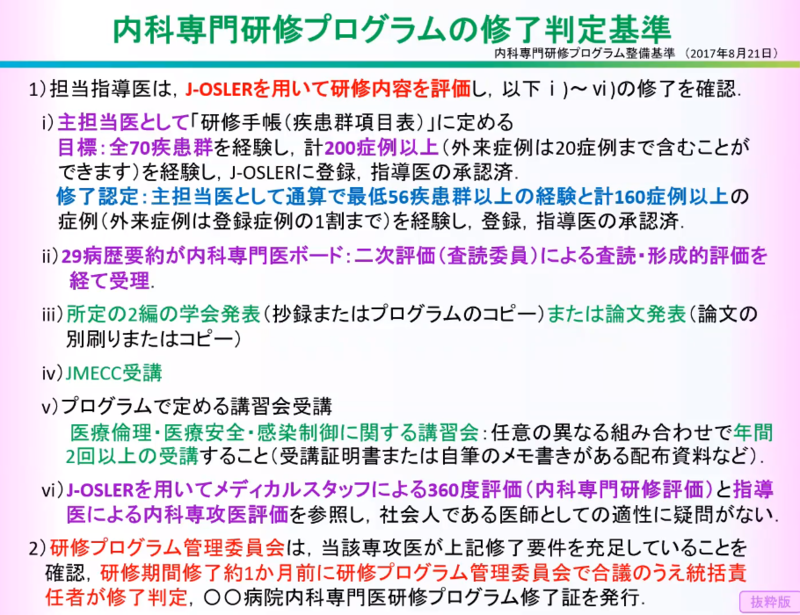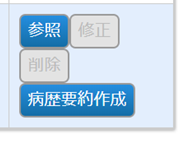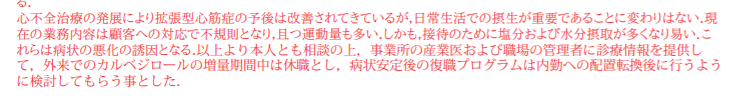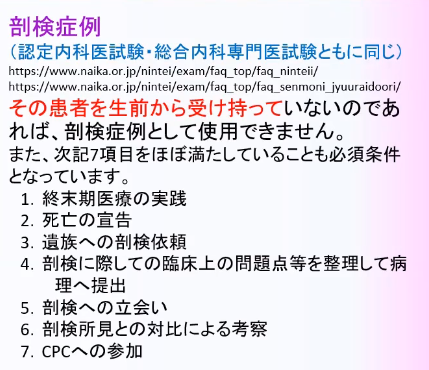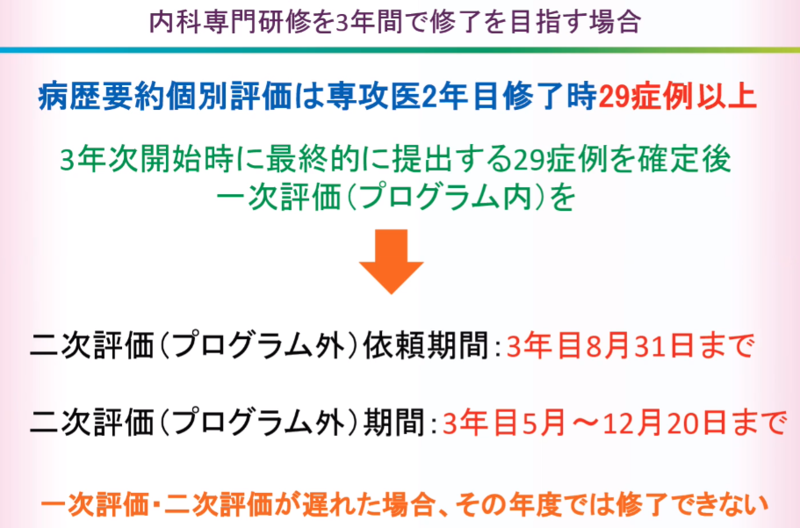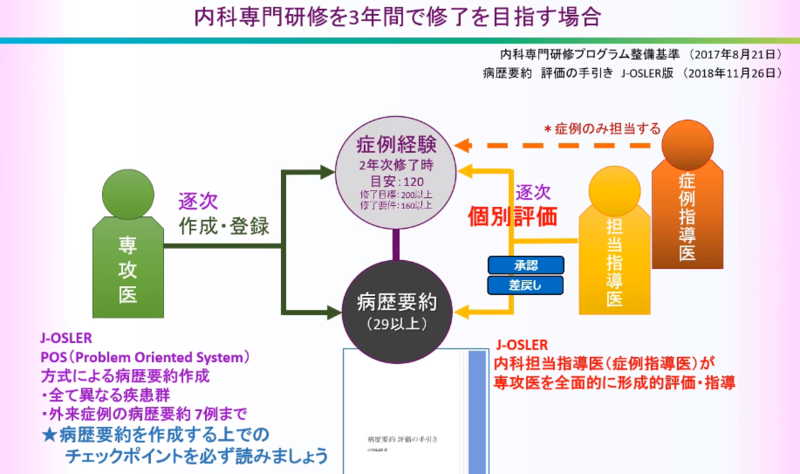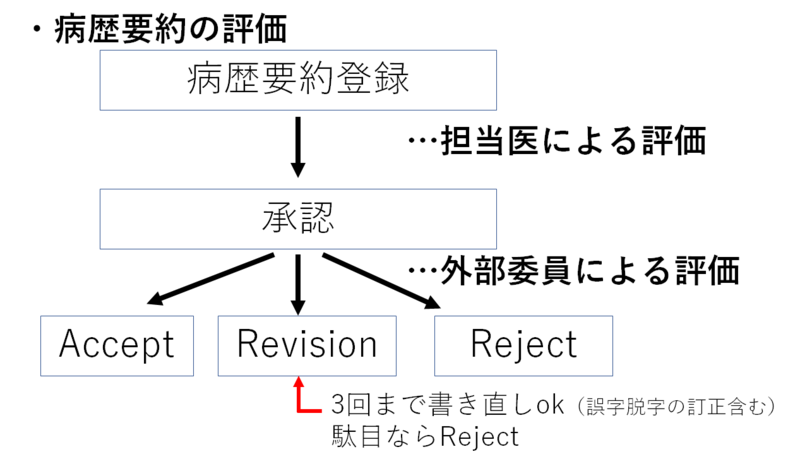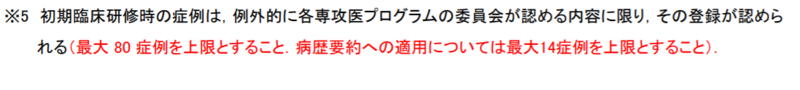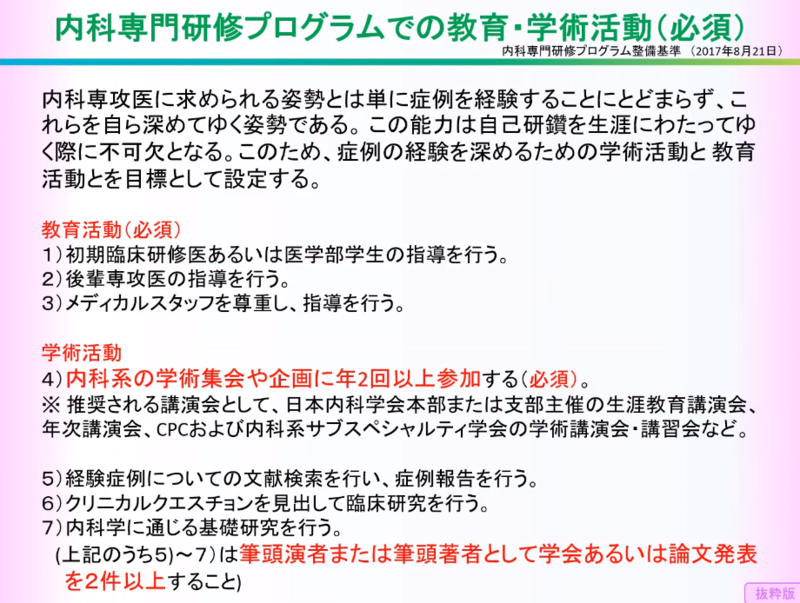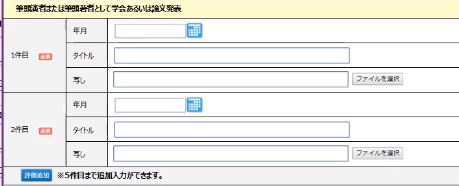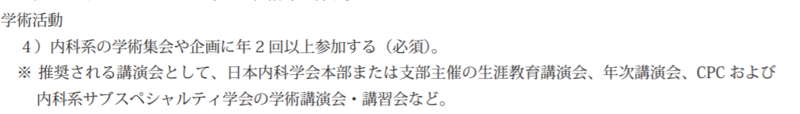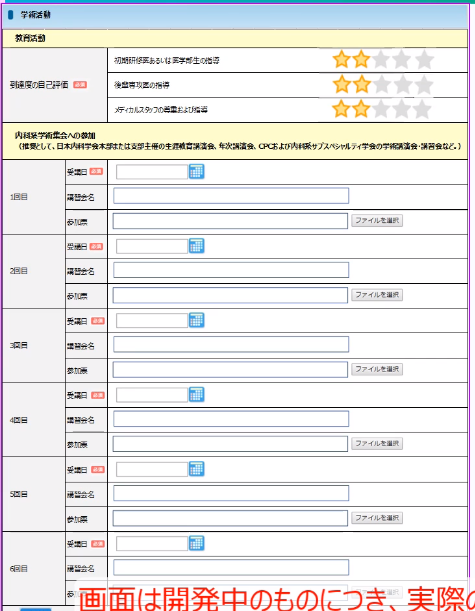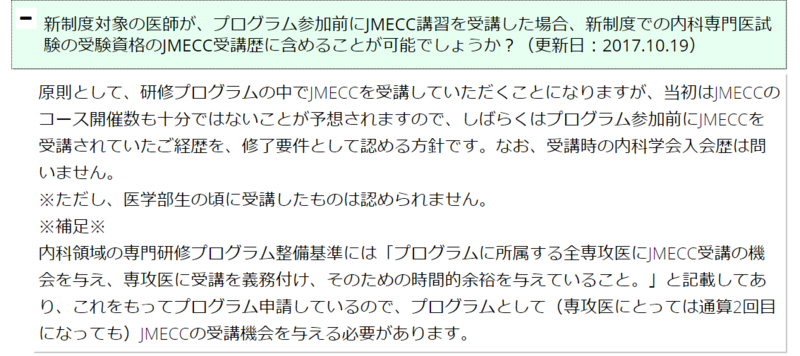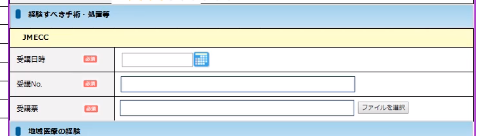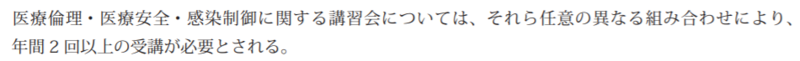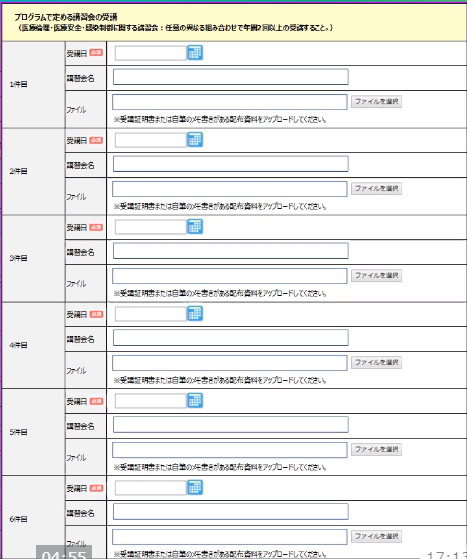訳あって、専門医プログラムの進捗確認の仕事をしているので、情報整理踏まえて。
恐ろしいほどに面倒な制度です。J-oslerに皆目が行きがちですが、他の条件も相当に面倒なので、確認が重要。
※2020/3/13症例登録テンプレURL更新しました
-
情報は主に
-
「 専門研修プログラム整備基準【内科領域】」: https://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/2018/09/2017-program.pdf
-
「病歴要約評価と修了判定(病歴要約評価の流れを中心に)」: https://www.naika.or.jp/nintei/j-osler/judgment/ より。
-
一部補足で学会に筆者が確認した部分もあります。
-
詳細に関しては学会に直接聞かれることをおすすめします。この文に関して生じた不利益に関しては、一切責任を負いかねます。
修了条件は以下の通り。
まとめると以下の通り
-
症例登録を160症例(56疾患群)実施する
-
29篇の病歴要約を受理される
-
学会発表または論文発表を2回実施+学会に参加する(※年2回、3年間で6回)
-
JMECC受講
-
年2回以上の講習会参加(3年で6回)
-
360度評価
360度評価に関しては専攻医の考えることではないため、1-5が専攻医にとっては重要となる。
1. 症例登録
-
症例の概略(退院サマリーレベル)を160症例(56分野以上)登録する必要がある
-
記載すべき項目は多いが、「必須」なのは以下のみ
-
患者情報(年齢・入院期間など)
-
疾患項目
-
プロブレム(最低1個):100字以内
-
症例の概要:500字以内
-
症例を経験しての自己省察:300字以内
-
また、外部委員の目が入らない部分でもある。
-
退院サマリーを利用してとにかく数を稼ぐことが重要
-
56分野(参考: http://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/2015/08/2015-log.pdf)さえ満たしていればいいので、逆に言えば104症例(160症例-56疾患群)は同じ疾患であっても理論的には大丈夫!?
-
内科認定医時代は18例であったが、新制度では29例となった。
-
①の症例登録を実施した症例でのみ、病歴要約が作れるという2階建て方式となっている
-
Web上で入力するため、余白の調整等は不可能。
-
評価の手引で繰り返し書かれていることは考察に「全人的な視点」があること、とある。
-
内容としては29症例(うち2例外科紹介症例、1例剖検)であり、特に厄介なのが剖検症例。
-
最終タイムリミット(外部委員への審査期限)は3年目の8/31となっており、評価は12/20までに終わらせる必要あり
-
評価のイメージ(独自作成)
※1-2J-oslerに関して追記
-
内科学会は「症例登録週1-2例」・「病歴要約月2-3例」をコンスタントにやること、と説明しているが、そんなことをしている内科専攻医はこの世にいるのだろうか?
-
どちらも初期研修医のものは「半分使える」(症例登録80、病歴要約14)ことが明記されているので、内科になりたい初期研修医はEPOC作るついでに、Joslerも進めておくべき(Joslerは使えないので、Word等で書いて貯めておく形にはなる)
-
テンプレ:
ここまではよく言われていることだが、ここから先(Josler以外)にも色々面倒な条件がある。
3.学会発表または論文発表を2回実施+学会に参加する(※年2回、3年間で6回)
-
所定の2編の学会発表または論文発表
-
学会と言っても何でもいいわけではない模様。
-
目安としては
-
日本医学会連合加盟学会 https://www.jmsf.or.jp/memberslist.html
-
抄録or論文を後々Joslerで登録する(模様)…https://www.naika.or.jp/nintei/j-osler/judgment/ 17:31
-
学会に参加参加する
-
修了条件には詳しく書かれていないが、「必須条件の一つ」。
-
年2回、つまりプログラム中計6回の参加が必要(学会確認済み)
-
https://www.naika.or.jp/nintei/j-osler/judgment/ 16:42でも必須条件として書かれている。
-
登録方法は学会参加症または領収書とのこと(学会確認済み)
4.JMECC受講
-
初期研修医時代のものであっても認定される模様( https://jmecc.net/faq/ より)
-
Joslerに受講票を提出する模様
5.講習会参加
-
病院で実施される講習会(医療倫理など)を年2回=プログラム3年間中で6回参加する
-
「受講証明書または自筆のメモ書きのある配布資料」をJoslerで提出する模様(メモ書きのある配布資料とは???)
ということで、非常にJosler以外にも面倒くさい(積み立てていかなければならない)条件があるということだった。
個別アドバイスとしては
-
新後期研修医3年目
-
とにかく夏までにJoslerを終わらせて、指導医の評価まで完了しておく
-
学会発表・参加を確認し、足りなければ早急に参加登録する(コロナの影響で中止になる学会も多いため、秋以降の学会のほうがいいかもしれない)
-
講習会に計6回になるよう参加する
-
新後期研修医1,2年目
-
2年目終了までにJoslerを終わらせる(気持ちで頑張る)
-
学会・JMECC・講習会参加予定を予めスケジュールしておく
-
内科になりたい初期研修医
-
終了条件を予めチェックし、後期1年目の学会のスケジュールを立てておく
-
Josler雛形を作る
-
自作テンプレ 使ってください
-
JMECCに参加しておく
-
内科を考えている医学生
-
結構面倒な制度です。少しは条件が変わっているかもしれませんが、「計画性」か「終盤の爆発力」が必要な制度であることは間違いないと思います。
です。しゃにむに頑張りましょう。